
|
|
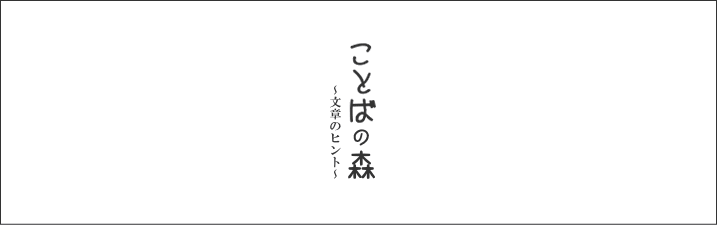 |
|
|
|
|
|
| |
|
■最後の一文で「隠れテーマ」を一瞬にして浮かび上がらせる
~向田邦子『父の詫び状』にみる文章テクニック~
|
| |
|
|
|
|
|
|
いわずと知れた向田邦子の『父の詫び状』。読んだことがある人も多いでしょう。実はこのエッセイは、文章を書くことを生業とする人間からすると信じられないほど巧みな文章構成になっています。エッセイストや小説家として食べている人でも、このような文章を書ける人はほとんどいないといってもいいでしょう。
ではこのエッセイの何がスゴいのかというと、「バラバラなエピソードを最後の一文でまとめ上げる力」がハンパでないことです。バラバラのビーズを、スーっと糸を通して一瞬にして首飾りにしてしまう力、とでもいうのでしょうか。読んでいる側からすると、何か魔法にかかったかのような感覚すら覚えるのです。では、どうしたらこのような文章が書けるのでしょうか。あえて挑戦してみましょう。
『父の詫び状』は主に次のA~Eの5つのエピソードからなっています。
A:最近、伊勢海老を知人からもらったら、海老が逃げて玄関にシミができた。
B:昔、「お客様は何人?」と父に訊いたら「なんのために靴を揃えているのか!」と玄関で怒られた。
C:母から、なぜ父が靴を揃えずに脱ぐのか理由を聞いたことがある。
D:父が犬に向かって蹴り上げたら靴が工場に入ってしまい、自分が取りに行った。父はしばらく知らんぷりをしていた。
E:親の住む仙台の家のお客の吐しゃ物を片付けていたら父が後ろで黙ってみていた。
話はどんどん飛躍し、次々と異なるエピソードを紹介されていきます。読者はいったいどこに連れて行かれるのかさっぱりわかりません。エピソードで唯一共通するのは「玄関と靴」に関するものだということです。でも「だから何?」という感がずっとぬぐえません。
ところがです。最後に、向田邦子が仙台の家から下宿をしていた東京に帰ったとき、『「このたびは格別の御働き」という一行があり、そこだけ朱筆で傍線が引かれてあった。それが父の詫び状だった』と記され、読者はこのエッセイが実は「頑固で不器用な父が詫びる物語」だったことに初めて気づかされることになります。
「玄関と靴」という共通項でかろうじて文章が拡散してしまうのを防ぎ、次々とエピソードを変えて読者に混乱を与えつつも、その下では「頑固で不器用な父が詫びる物語」のための仕込みが着々となされていたのです。Bの「怒る父」、Dの「知らんぷりをする父」、Eの「無言の父」などを登場させて伏線を張り、最後の最後に「それが父の詫び状だった」の一文で一気に仕留めているのです。
読者に「玄関と靴」に関するエッセイとだと表向き思わせておいて、読者に気づかれないように隠れテーマが仕込まれており、最後の一文でそれを一気に浮かび上がらせる。魔法にかかったような感覚を覚えるのはそのためでしょう。図にすると、下のような構図になっています。
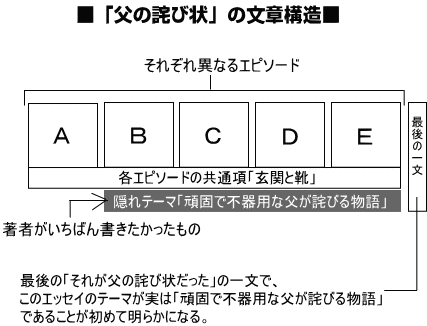
向田流、隠れテーマを最後の一文でポンを浮かび上がらせるポイントは次の4つです。
・各エピソードをバラバラの内容にする
・バラバラなエピソードを提示しながら、1つ共通点をもたせる(拡散しないため)
・バラバラなエピソードで読者を混乱させながら、メインテーマの仕込みをしておく
・最後に、隠れテーマを浮かび上がらせる言葉で締める
はっきりいってかなり高度です。一度でうまくいくことはまずないでしょう。でもこれが習得できたら、プロ並みの、あるいはそれ以上の文章力を手に入れることができるはずです。
ぜひ、向田テクニックを駆使して名文を書いてみてください。
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
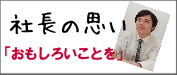 |
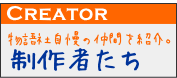 |
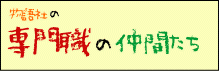 |
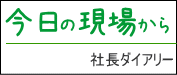 |
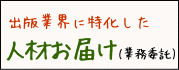 |
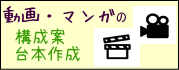 |
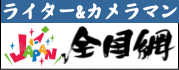
|
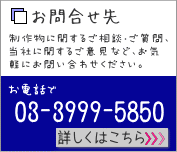 |
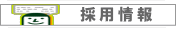 |
 |
| |
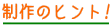

「ことば」は使い方次第で、人の心を動かす大きな武器になります。ことばはどのように使うべきなのか。そのヒントをお伝えいたします。 |
|

「いいデザイン」とされるものには共通したある特徴があります。デザインのコツをお伝えします。
|
|
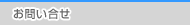 |
|
|
|
|
株式会社物語社
〒176-0023
東京都練馬区中村北2-22-19-301 |
|
|
|
 |
|